先日、例によって、面白い動画を見ました。
▶️ 【読み聞かせの効果はたった5%】遺伝に勝つ親の行動/英才教育は遺伝に勝てるのか?
タイトルだけ見て「え、読み聞かせって無意味だったの?」と一瞬焦りました。
✅ 結論から言うと:
教育は「遺伝に勝つ」ものではない。
でも、教育がなければ、遺伝的素質は発現すらしない。
つまり、親にできることは「勝たせる」ことではなく、
能力を伸ばす“余白と空気”を整えることです。
📌 要点まとめ
🔹 性格や知能のベースは遺伝
- 知能の約67%、性格の約50%は遺伝で説明される。
- “家庭環境(共有環境)”の影響はかなり限定的。
📖 Plomin & Deary (2015), Bouchard & Loehlin (2001)
🔹 それでも親にできることはある
- 非共有環境(その子だけの経験)が性格や能力の表れ方に影響。
- 親の役割は「変える」ことではなく、“引き出す場”を用意すること。
🔹 読み聞かせは、学力ブースターではなく、機会提供
- 学力効果は最大5%ほど。ただし、語彙力・共感力・親子関係にはプラス。
📖 Reading Rockets / ASCD / Wilhelm et al. (2013)
🔹 興味の芽を摘まない/強制は逆効果
- 「やりなさい」より、「やれる環境」の方が自発性を引き出す。
- 興味のあるものを“見える場所”に置くだけでも効果あり。
📖 Deci & Ryan (2000)
🔹 親の生き方そのものが、最大の教育
- 子どもは言葉より「親の姿勢」から学ぶ。
- 四六時中コントロールするより、自分が楽しそうに生きることが教育になる。
📝 結論:勝ち負けじゃなくて「引き出す」視点で
教育を「勝つ・負ける」で考えるとしんどくなります。
でも、“その子の持ってる力を、ちゃんと引き出してあげる”って視点で見直すと、
毎日のちょっとした関わりが、ちゃんと意味を持ってくるのかな、と。
ということで、寝る前の数分の読み聞かせ時間、あらためて、大事にしていこうと思いました。
以上、念のため共有まで。
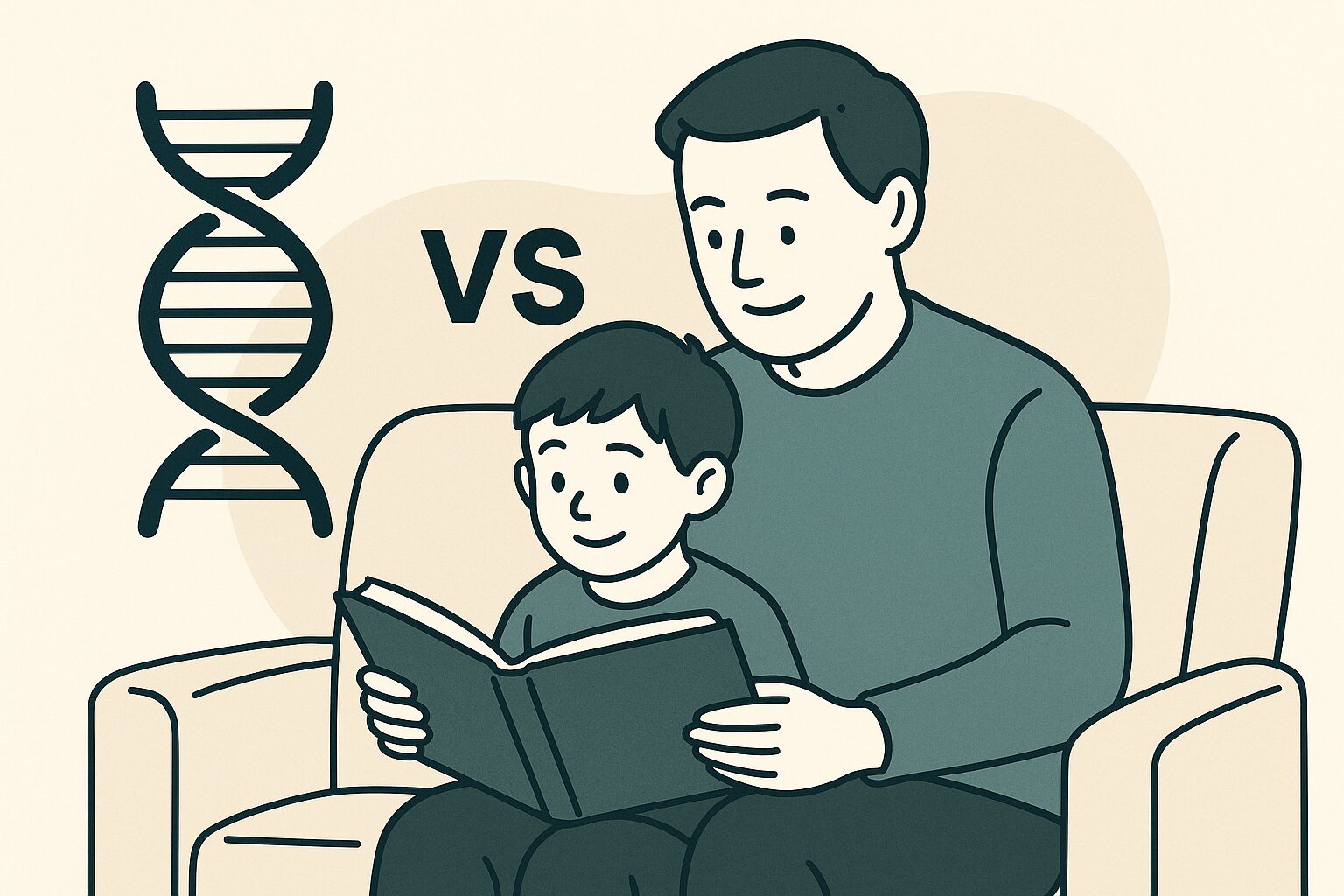

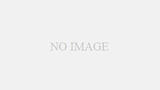
コメント